
今度、ピアノの課題曲がドビュッシーの「子供の領分」になりまして、ただいま譜読みの真っ最中なのですが、ここで面白いことを発見しましたのでブログに記したいと思います。(ところでこの組曲の一曲目、最近テレビのCMに起用されてますね。家電製品だったような…。)
子供の領分は6曲から成る組曲ですが、一番最後の「ゴリヴォーグのケークウォーク」が「エンターテイナー」等で有名なラグタイムの音楽にそっくりなんです。A-B-A-C-Dを中心としたラグタイムの構成は違うのですが、ルートとコードを交互に左手で弾くストライド奏法や、シンコペーションのリズムなどがまさにそっくりです。
調べてみると、タイトルにもあるケークウォークとは20世紀の初めにフランスの黒人の間で流行したダンスのことで、これがフランス人女性たちにもウケていたそうです。作曲家のクロード・ドビュッシーはパリの万国博覧会で聴いたガムランや日本の水墨画など海外の芸術を自分の作品に取り入れた国際派です。黒人文化も彼にとって斬新な素材だったのかもしれません。
ではフランス音楽はアフリカ文化の恩恵に授かっているだけかというとそうでもありません。ほぼ同時期にアメリカで流行っていたラグタイムは、やはり黒人文化と西洋音楽の融合体で、その後発展を続け、ルイ・アームストロングらのポリフォニックジャズ、ビッグ・バンド主流のスイング時代、チャーリー・パーカーらを中心としたビバップと形を変えていきます。総じてジャズはフランス音楽の影響を確実に受けていると見られます。その要素の一つが長7度です。
現代では当たり前となったメジャーセブンスコード(CM7、C△7など)は、バロックから古典派やロマン派まではほとんど使われることはありませんでした。長7度とはルートの半音だけ下の音なので不協和音と考えられていたのでしょう。ロマン派になって、フランツ・リストが9度や13度を用いるようになりましたが、長7度が顕著に聴こえるようになったのはサティ、ドビュッシー、ラヴェルなど20世紀の音楽家の作品です。偉大な作曲家は常に新しい音楽を求めて創作し続けましたが、ルートとわずか半音となりの長7度の響きが認められるようになるまではそれなりの時間と段階が必要だったようです。
ジャズの世界でもこの長7度は、特にバラードなどハーモニーを重視した曲に見られます。中でもエロール・ガーナー作曲のミスティは、Look at me〜と歌い出す「me」の音が長7度です。ドビュッシーの「夢」をカヴァーした「Eroll's Reverie」を録音していたことから、フランス音楽を好んでいたのではないかと思われます。その他のスタンダードでも「I Remember You」、「I Can't Get Started」など長7度をメロディに用いた曲はたくさんあります。
そして、ジャズがフランス音楽から受けた最も大きな影響はモードの採用でしょう。ピアニスト、ビル・エバンスによりマイルス・デイビスに紹介・採用され、爆発的に広まったこの技法は、ジャズの地位を単なるエンターテイメントから芸術の域まで押し上げました。その後、ハービー・ハンコックやチック・コリアなどのピアニストたちに受け継がれ、それぞれスタイルを変えながら発展していきます。
また、アメリカのジャズアーティストたちは数多くパリを訪れ録音を残しています。バド・パウエル、ビル・エバンス、オスカー・ピーターソン、マイルス・デイビス、キース・ジャレットなど、名前を上げるときりがありません。
その反対に、フランスも素晴らしいジャズミュージシャンを多数生み出し、ニューヨークへ送り出しています。ステファン・グラッペリをはじめ、ミシェル・ペトルチアーニ、フレンチ・ジャズ・トリオなどがそうです。
20世紀の初めに生まれた音楽は、アメリカとフランスでそれぞれ発展し平行線をたどりながらも、互いに刺激しあっているように思います。もちろんどちらも素晴らしい音楽ですので、今後の展開が楽しみです。
子供の領分、月曜日まで譜読み…。まだ6曲中2曲目…(-_-;)。


























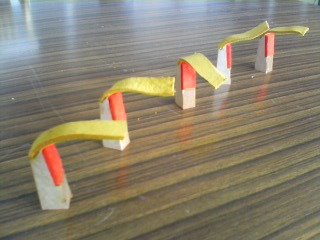








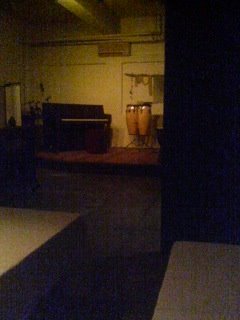













 JazzPianoLab.com
JazzPianoLab.com
 人気blogランキングへ
人気blogランキングへ

